こんにちは。いりこです。
5年に一度開催される、世界一の知名度と権威を誇るショパン国際コンクールが2025年に開催されます。
2025年は大コンクールイヤー!
こちらの記事でまとめた15のコンクールのうち7つが開催されました。
ショパン国際と同じく「世界三大コンクール」と称されるエリザベート王妃国際に加え、バッハ国際、ロン=ティボー国際、クライバーン国際(特集なし)、ブゾーニ国際、クララ・ハスキル国際とみてきました。
そしていよいよ最高峰ショパン国際コンクール!84名でスタートした1次ラウンドから、今日からの3次ラウンドでは20名まで絞られました。
2日目、筆者の大注目17歳Tianyao Lyu、地元ポーランド勢のPiotr PawlakにYehuda Prokopowicz、マレーシアからのVincent Ongそして我らが進藤 実優さんに注目!
※Eric Luは体調不良のため3日目に演奏。
ショパン国際ピアノコンクール概要
公式HP(英語・ポーランド語):https://konkursy.nifc.pl/en/miedzynarodowy/konkurs
公式YouTube:https://www.youtube.com/@chopininstitute
知名度も権威も世界一と言っていい超名門ピアノコンクール。
大作曲家ショパンの名を冠し、祖国ポーランドが国を挙げて開催しているコンクールです。
演奏されるのはショパンの曲のみ!もちろんピアノ部門のみ!という独特なコンクールでもあります。5年に1度と開催間隔もかなり長く、歴史も長いです。
2020年はコロナで延期、満を持して開催された2021年大会は、反田と小林がW入賞して話題になりました。優勝者のブルース・リウ、ガジェヴやガルシアなど、タレント揃いで見ごたえのある大会でした。
- 概要
開催地:ワルシャワ(ポーランド)
開催期間:2025年10月2日(木)~ 10月23日(木)
開催間隔:5年に1度(第18回:2021年10月(2020年から延期)、次回:2025年)
歴史:第1回1927年

ちなみに過去の優勝者・入賞者は、クラシック界をけん引する錚々たるメンツ。名前を眺めるだけで鳥肌が立ちます!(笑)
- 主な優勝者・入賞者
優勝者:マウリツィオ・ポリーニ(1960)、マルタ・アルゲリッチ(1965)、ギャリック・オールソン(1970)、クリスティアン・ツィメルマン(1975)、ダン・タイ・ソン(1980)、スタニスラフ・ブーニン(1985)、ユンディ・リ(2000)、ラファウ・ブレハッチ(2005)、ユリアンナ・アヴデーエワ(2010)、チョ・ソンジン(2015)、ブルース・リウ(2021)
入賞者:ウラディミール・アシュケナージ(1955年第2位)、アルトゥール・モレイラ・リマ(1965年第2位)、内田 光子(1970年第2位)、横山 幸雄(1990年第3位)、ダニール・トリフォノフ(2010年第3位)、反田 恭平(2021年第2位)、マルティン・ガルシア・ガルシア(2021年第3位)、小林 愛実(2021年第4位)
▼過去大会の振り返り記事も併せてご覧ください!
2010年ショパンコンクールに耽る~アヴデーエワ/ゲニューシャス/トリフォノフ/デュモン~
2015年ショパンコンクールを振り返る~チョ・ソンジン/アムラン/ケイト・リウ/エリック・ルー/(トニー)・ヤン/シシュキン~
2021年ショパンコンクールを振り返る~ブルース・リウ/反田恭平/ガルシア・ガルシア/小林愛実/クシュリク/アルメリーニ/ラオ・ハオ~
スケジュール
予備予選(160名):2025年4月23日(水)~ 5月4日(日)
1次ラウンド(84名):2025年10月3日(金)~ 7日(火)
2次ラウンド(40名):2025年10月9日(木)~ 12日(日)
3次ラウンド(20名):2025年10月14日(火)~ 16日(木)10月14日(火)10:00(日本時間17:00)、17:00(翌0:00)
10月15日(水)10:00(日本時間17:00)、17:00(翌0:00)
10月16日(木)10:00(日本時間17:00)、17:00(翌0:00)
10月17日(金):ショパン没後176年目の命日
ファイナル(10名):2025年10月18日(土)~ 20日(月)
20日近くに及ぶ長丁場です。
プログラム
レパートリー:
参加者は、ビデオ審査で演奏した曲を本大会で演奏できる。
また、予備予選で演奏した曲も本大会で演奏できる(ただし練習曲を除く)。
本大会においては、同じ曲を異なるラウンドで演奏することはできない。
▼前回大会からの変更点を詳しく解説
【課題曲に大幅変更!】第19回(2025年)ショパン国際コンクール募集要項発表
3次ラウンド(20名)
• Sonata in B flat minor, Op. 35 or Sonata in B minor, Op. 58
/ソナタ第2番 変ロ短調 または ソナタ第3番 ロ短調
The exposition in the first movement of both Sonatas should not be repeated.
/いずれのソナタも、第1楽章提示部はリピートしないこと
• a full set of Mazurkas from the following opuses:/以下の作品番号のマズルカから1セット全曲
17, 24, 30, 33, 41, 50, 56, 59
The Mazurkas must be played in the order in which they are numbered in the opus. In the case of Opuses 33 and 41, the following numbering applies:
/マズルカは作品番号で付けられた順番で演奏しなければならない。作品33、41の場合は、以下の番号が適応される。
Op. 33
No. 1 in G sharp minor
No. 2 in C major
No. 3 in D major
No. 4 in B minor
Op. 41
No. 1 in E minor
No. 2 in B major
No. 3 in A flat major
No. 4 in C sharp minor
• any other solo piece or pieces by Fryderyk Chopin (if the hitherto performed repertoire does not achieve the minimum performance time indicated below).
/ショパン作曲のソロ作品(それまでに演奏されたレパートリーが、以下に示す最小演奏時間に達しない場合)
Performance time in the third round: 45–55 minutes.
/演奏時間は45~55分
The pieces may be performed in any order (except the Mazurkas).
/演奏順は問わない(マズルカを除く)
10月15日(水)10:00(日本時間17:00)
▼全体版:今大会も休憩中に「ショパン・トーク」が開催されるようです!他の大会にはないエンタメ性、魅力を発信しつづける素晴らしい姿勢ですね。
Xiaoxuan Li (China, 2001) ※1次ラウンド ※2次ラウンド
piano: Steinway & Sons
Mazurka in G sharp minor Op. 33 No. 1
/マズルカ 嬰ト短調 Op. 33 No. 1
Mazurka in C major Op. 33 No. 2
/マズルカ ハ長調 Op. 33 No. 2
Mazurka in D major Op. 33 No. 3
/マズルカ ニ長調 Op. 33 No. 3
Mazurka in B minor Op. 33 No. 4
/マズルカ ロ短調 Op. 33 No. 4
Sonata in B flat minor Op. 35
/ピアノソナタ第2番 変ロ短調 Op. 35
Scherzo in C sharp minor Op. 39
/スケルツォ第3番 嬰ハ短調 Op. 39
細かいことですけど、ソナタ3楽章で、右手の装飾に合わせて左手のリズムを前倒しにしてましたが、正しい?あとは録音のせいかもですが、少し音がこもって聴こえる、こっちから音を聞きに行かないと聞こえない感じがしました。
Eric Lu (USA, 1997) ※1次ラウンド ※2次ラウンド
piano: Fazioli
※体調不良のため翌日16日に変更
Tianyao Lyu (China, 2008) ファイナル進出 ※1次ラウンド ※2次ラウンド
piano: Fazioli
Mazurka in A minor Op. 59 No. 1
/マズルカ イ短調 Op. 59 No. 1
Mazurka in A flat major Op. 59 No. 2
/マズルカ 変イ長調 Op. 59 No. 2
Mazurka in F sharp minor Op. 59 No. 3
/マズルカ 嬰ヘ短調 Op. 59 No. 3
Prelude in D flat major Op. 28 No. 15
/前奏曲第15番 変ニ長調 「雨だれ」 Op. 28 No. 15
Sonata in B flat minor Op. 35
/ピアノソナタ第2番 変ロ短調 Op. 35
Berceuse in D flat major Op. 57
/子守歌 変ニ長調 Op. 57
マズルカ、極端に緩急つけないあたりセンスがいい。一転、ソナタではヒステリックで強烈な印象がありました。マズルカの後に挿入された雨だれは個人的にしっくり来なかったですが、最後は子守唄で終わり、若々しい曲満載だった2次ラウンドに続いてユニークなプログラム。
10月15日(水)17:00(日本時間 翌0:00)
▼全体版:休憩中の「ショパン・トーク」にも注目!
Vincent Ong (Malaysia, 2001) ファイナル進出 ※1次ラウンド ※2次ラウンド
piano: Shigeru Kawai
Variations in B flat major on a theme from Mozart’s ‘Don Giovanni’ (‘Là ci darem la mano’) Op. 2
/モーツァルト「ドン・ジョヴァンニ」の「お手をどうぞ」の主題による変奏曲 変ロ長調 Op. 2
Mazurka in E minor Op. 41 No. 1
/マズルカ ホ短調 Op. 41 No. 1
Mazurka in B major Op. 41 No. 2
/マズルカ ロ長調 Op. 41 No. 2
Mazurka in A flat major Op. 41 No. 3
/マズルカ 変イ長調 Op. 41 No. 3
Mazurka in C sharp minor Op. 41 No. 4
/マズルカ 嬰ハ短調 Op. 41 No. 4
Piano Sonata in B minor Op. 58
/ピアノソナタ第3番 ロ短調 Op. 58
これまた独特な演奏でしたね。ラチダレムなどショパンの若い曲に当てるともったり聴こえてしまいましたが、マズルカやピアノソナタはなかなかおもしろかったです。特にマズルカは、抒情性が全面に出ているわけでもなく、舞踏性があったわけでもないですが、なんというべきか、生活感を浴びている感じ、おもしろい体験でした。
Piotr Pawlak (Poland, 1998) ※1次ラウンド ※2次ラウンド
piano: Shigeru Kawai
Rondo à la Krakowiak in F major Op. 14
/ロンド・ア・ラ・クラコヴィヤク ヘ長調 Op. 14
Mazurka in B flat major Op. 17 No. 1
/マズルカ 変ロ長調 Op. 17 No. 1
Mazurka in E minor Op. 17 No. 2
/マズルカ ホ短調 Op. 17 No. 2
Mazurka in A flat major Op. 17 No. 3
/マズルカ 変イ長調 Op. 17 No. 3
Mazurka in A minor Op. 17 No. 4
/マズルカ イ短調 Op. 17 No. 4
Piano Sonata in B minor Op. 58
/ピアノソナタ第3番 ロ短調 Op. 58
2次ラウンドでの演奏会用アレグロに続き、「ロンド・ア・ラ・クラコヴィアク」というマイナーな大曲。これは恥ずかしながら聴いた記憶がないです。序奏のなんと澄んだユニゾン。秋のポーランドの田舎の風景が勝手に脳内に流れこんできますね。そこから民族的・舞踏的、そして若いショパンらしい快活な音楽で、15分くらい?の曲があっという間に終わっていました。そこから間髪入れずにマズルカ。ここまではとってもよかったのですが、ピアノソナタが鬼門。もともとレトロ録音のような大らかさだとは思っていましたが、3楽章以外は準備が間に合っていない(のか弾けてない)。んー、飛び抜けた音楽性をもってもお釣りがくるのか微妙なところ。。。期待したいですが協奏曲まで持つのかは怪しい気もします。
Yehuda Prokopowicz (Poland, 2005) ※1次ラウンド ※2次ラウンド
piano: Steinway & Sons
Mazurka in G sharp minor Op. 33 No. 1
/マズルカ 嬰ト短調 Op. 33 No. 1
Mazurka in C major Op. 33 No. 2
/マズルカ ハ長調 Op. 33 No. 2
Mazurka in D major Op. 33 No. 3
/マズルカ ニ長調 Op. 33 No. 3
Mazurka in B minor Op. 33 No. 4
/マズルカ ロ短調 Op. 33 No. 4
Scherzo in E major Op. 54
/スケルツォ第4番 ホ長調 Op. 54
Berceuse in D flat major Op. 57
/子守歌 変ニ長調 Op. 57
Sonata in B flat minor Op. 35
/ピアノソナタ第2番 変ロ短調 Op. 35
ポーランドのピアニストが弾けば正解なんでしょうけども、マズルカはちょっと間延びしていた気もします。1次から大崩れしない安定感はありますが、このレベルになると少し埋もれてしまうのかなという印象。
Miyu Shindo (Japan, 2002) ファイナル進出 ※1次ラウンド ※2次ラウンド
piano: Steinway & Sons
Mazurka in B major Op. 56 No. 1
/マズルカ ロ長調 Op. 56 No. 1
Mazurka in C major Op. 56 No. 2
/マズルカ ハ長調 Op. 56 No. 2
Mazurka in C minor Op. 56 No. 3
/マズルカ ハ短調 Op. 56 No. 3
Sonata in B flat minor Op. 35
/ピアノソナタ第2番 変ロ短調 Op. 35
Andante spianato and Grande Polonaise Brillante in E flat major Op. 22
/アンダンテ・スピアナートと華麗なる大ポロネーズ 変ホ長調 Op. 22
さて日本人二人目は進藤さん。前回2021年大会の3次ラウンドのソナタ3番はよく覚えていますが、今回はソナタ2番とアンスピ&大ポロネーズ。ここまで安定感をもってラウンドを進めているのはさすがの貫禄ですね。まだお若いのがびっくりします。
2日目まとめ
2日目お疲れさまでした🙇
Tianyao Lyuはこれまでほどの衝撃はないもののかなり完成度が高いですね、推しの一人。地元ポーランド勢のPiotr Pawlakさん、ロンドクラコヴィアク→マズルカの流れは圧巻でしたが、ソナタ、それからファイナルに行った場合の協奏曲はやや不安。これまた独特なVincent Ongさんに安定感が光った進藤 実優さんと、昨日に引き続き見ごたえのある一日でした!

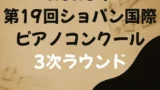


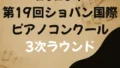
コメント