こんにちは。いりこです。
5年に一度開催される、世界一の知名度と権威を誇るショパン国際コンクールが2025年に開催されます。
2025年は大コンクールイヤー!
こちらの記事でまとめた15のコンクールのうち7つが開催されました。
ショパン国際と同じく「世界三大コンクール」と称されるエリザベート王妃国際に加え、バッハ国際、ロン=ティボー国際、クライバーン国際(特集なし)、ブゾーニ国際、クララ・ハスキル国際とみてきました。
そしていよいよ最高峰ショパン国際コンクール!5日間におよんだ1次ラウンドを経て、半分の40名が通過しました。
2次ラウンドも最終日、Yehuda Prokopowicz、Hao Rao、Anthony Ratinov、進藤 実優、Gabriele Strata、牛田 智大、Zitong Wang、山縣 美季と筆者的に優勝候補ひしめく大忙し日!
ショパン国際ピアノコンクール概要
公式HP(英語・ポーランド語):https://konkursy.nifc.pl/en/miedzynarodowy/konkurs
公式YouTube:https://www.youtube.com/@chopininstitute
知名度も権威も世界一と言っていい超名門ピアノコンクール。
大作曲家ショパンの名を冠し、祖国ポーランドが国を挙げて開催しているコンクールです。
演奏されるのはショパンの曲のみ!もちろんピアノ部門のみ!という独特なコンクールでもあります。5年に1度と開催間隔もかなり長く、歴史も長いです。
2020年はコロナで延期、満を持して開催された2021年大会は、反田と小林がW入賞して話題になりました。優勝者のブルース・リウ、ガジェヴやガルシアなど、タレント揃いで見ごたえのある大会でした。
- 概要
開催地:ワルシャワ(ポーランド)
開催期間:2025年10月2日(木)~ 10月23日(木)
開催間隔:5年に1度(第18回:2021年10月(2020年から延期)、次回:2025年)
歴史:第1回1927年

ちなみに過去の優勝者・入賞者は、クラシック界をけん引する錚々たるメンツ。名前を眺めるだけで鳥肌が立ちます!(笑)
- 主な優勝者・入賞者
優勝者:マウリツィオ・ポリーニ(1960)、マルタ・アルゲリッチ(1965)、ギャリック・オールソン(1970)、クリスティアン・ツィメルマン(1975)、ダン・タイ・ソン(1980)、スタニスラフ・ブーニン(1985)、ユンディ・リ(2000)、ラファウ・ブレハッチ(2005)、ユリアンナ・アヴデーエワ(2010)、チョ・ソンジン(2015)、ブルース・リウ(2021)
入賞者:ウラディミール・アシュケナージ(1955年第2位)、アルトゥール・モレイラ・リマ(1965年第2位)、内田 光子(1970年第2位)、横山 幸雄(1990年第3位)、ダニール・トリフォノフ(2010年第3位)、反田 恭平(2021年第2位)、マルティン・ガルシア・ガルシア(2021年第3位)、小林 愛実(2021年第4位)
▼過去大会の振り返り記事も併せてご覧ください!
2010年ショパンコンクールに耽る~アヴデーエワ/ゲニューシャス/トリフォノフ/デュモン~
2015年ショパンコンクールを振り返る~チョ・ソンジン/アムラン/ケイト・リウ/エリック・ルー/(トニー)・ヤン/シシュキン~
2021年ショパンコンクールを振り返る~ブルース・リウ/反田恭平/ガルシア・ガルシア/小林愛実/クシュリク/アルメリーニ/ラオ・ハオ~
スケジュール
予備予選(160名):2025年4月23日(水)~ 5月4日(日)
1次ラウンド(84名):2025年10月3日(金)~ 7日(火)
2次ラウンド(40名):2025年10月9日(木)~ 12日(日)10月9日(木)10:00(日本時間17:00)、17:00(翌0:00)
10月10日(金)10:00(日本時間17:00)、17:00(翌0:00)
10月11日(土)10:00(日本時間17:00)、17:00(翌0:00)
10月12日(日)10:00(日本時間17:00)、17:00(翌0:00)
3次ラウンド(20名):2025年10月14日(火)~ 16日(木)
10月17日(金):ショパン没後176年目の命日
ファイナル(10名):2025年10月18日(土)~ 20日(月)
20日近くに及ぶ長丁場です。
プログラム
レパートリー:
参加者は、ビデオ審査で演奏した曲を本大会で演奏できる。
また、予備予選で演奏した曲も本大会で演奏できる(ただし練習曲を除く)。
本大会においては、同じ曲を異なるラウンドで演奏することはできない。
▼前回大会からの変更点を詳しく解説
【課題曲に大幅変更!】第19回(2025年)ショパン国際コンクール募集要項発表
2次ラウンド(40名)
• 6 Preludes from Op. 28, consisting of one of the following three groups:
/前奏曲 Op.28から、以下3つのグループのうちの1つからなる6曲:
7–12 or 13–18 or 19–24
• one of the following Polonaises:/以下のポロネーズから1つ
Andante Spianato and Grande Polonaise brillante in E flat major, Op. 22/アンダンテ・スピアナートと華麗なる大ポロネーズ 変ホ長調
Polonaise in F sharp minor, Op. 44/ポロネーズ第5番 嬰ヘ短調
Polonaise in A flat major, Op. 53/ポロネーズ第6番 変イ長調(英雄)
or both Polonaises from Op. 26/ポロネーズ第1・2番の両方
• any other solo piece or pieces by Fryderyk Chopin (the full Op. 28 is allowed).
/ショパン作曲の他のソロ作品(前奏曲 Op.28 全曲も可)
Performance time in the second round: 40–50 minutes.
/演奏時間は40~50分
The pieces may be performed in any order (except Op. 26).
/演奏順は問わない(ポロネーズ Op.26 を除く)
10月12日(日)10:00(日本時間17:00)
▼全体版:今大会も休憩中に「ショパン・トーク」が開催されるようです!他の大会にはないエンタメ性、魅力を発信しつづける素晴らしい姿勢ですね。
Yehuda Prokopowicz (Poland, 2005) 3次ラウンド進出 ※1次ラウンド
piano: Steinway & Sons
Ballade in F major Op. 38
/バラード第2番 ヘ長調 Op. 38
Mazurkas Op. 17 Nos. 1–4
/マズルカ Op. 17 No. 1–4
Rondo à la Mazur in F major Op. 5
/マズルカ風ロンド ヘ長調 Op. 5
Preludes Op. 28 Nos. 19–24
/前奏曲 Op. 28 No. 19–24
Polonaise in A flat major Op. 53
/ポロネーズ第6番 変イ長調 「英雄」 Op. 53
マズルカ風ロンドは意外にも初めてですね。ショパン初期の作品のなかでは人気の曲だというイメージでしたが。この曲も含め鋭さみたいなのがいまいち伝わってこなかった印象。
Hao Rao (China, 2004) ※1次ラウンド
piano: Steinway & Sons
Barcarolle in F sharp major Op. 60
/舟歌 嬰ヘ長調 Op. 60
Preludes Op. 28 Nos. 13–18
/前奏曲 Op. 28 No. 13–18
Scherzo in C sharp minor Op. 39
/スケルツォ第3番 嬰ハ短調 Op. 39
Andante spianato and Grande Polonaise Brillante in E flat major Op. 22
/アンダンテ・スピアナートと華麗なる大ポロネーズ 変ホ長調 Op. 22
前回大会ファイナリスト。序盤は少しヒヤヒヤしましたが、スケルツォ3番が特によかったですね。10年前に17歳で4位になったエリック・ルーもそうですけど、ハオ・ラオさんも前回はとにかく美しい音楽性が印象的でした。が、お二人とも今回はそこに混沌とした渦というか、切迫した表現が大きくなっている印象があります。ショパントークで「自分は太っているから手に厚みがある」とおっしゃっていましたが笑、まさに前奏曲18番からスケルツォ3番でのごつごつした重たい音色は衝撃でした。アンスピ大ポロで見せる彼の抒情性、そして弾き飛ばさない丁寧さがときに不気味に響くようなアプローチは健在。
Anthony Ratinov (USA, 1997) ※1次ラウンド
piano: Steinway & Sons
Impromptu in A flat major Op. 29
/即興曲第1番 変イ長調 Op. 29
Impromptu in F sharp major Op. 36
/即興曲第2番 嬰ヘ長調 Op. 36
Polonaise in F sharp minor Op. 44
/ポロネーズ第5番 嬰ヘ短調 Op. 44
Preludes Op. 28 Nos. 13–18
/前奏曲 Op. 28 No. 13–18
Scherzo in C sharp minor Op. 39
/スケルツォ第3番 嬰ハ短調 Op. 39
推しピアニスト。贔屓目なしに聴いても(あるいはハードルを爆上げして聴いても)非常に高いレベルでまとまっているピアニストだと思いますね。軽やかな即興曲2番、うねりのある2番、そして男性的なポロネーズ5番でもきちんと音が鳴っていますし、細かなニュアンスにも配慮されていながら、割とオーソドックスでクセがない演奏なのもポイントです。それにしても同じピアノでも全く音色が違うからおもしろいです。
Miyu Shindo (Japan, 2002) 3次ラウンド進出 ※1次ラウンド
piano: Steinway & Sons
24 Preludes Op. 28
/24の前奏曲 Op. 28
Polonaise in A flat major Op. 53
/ポロネーズ第6番 変イ長調 「英雄」 Op. 53
さて進藤さん。前奏曲全曲は結構選択者が多く、また時間的に英雄ポロネーズを選択せざるを得ない、今大会では”よくある”プログラムになってしまいましたが、その中でも際立っていましたね!1番ハ長調も筆者好みのストレートで多層的。彼女の好きなポイントは、前のラティノフさん同様、”打鍵が深い”感じがするんですよね。細かいパッセージもうやむやにならず、女性で手の大きさもありそうですが、和音もしっかり掴んでいる感じがすてき。突飛な表現もないのにこれだけ印象に残る演奏は素晴らしいと思います。
Gabriele Strata (Italy, 1999) ※1次ラウンド
piano: Steinway & Sons
Bolero in A minor Op. 19
/ボレロ イ短調 Op. 19
Preludes Op. 28 Nos. 7–12
/前奏曲 Op. 28 No. 7–12
Polonaise in F sharp minor Op. 44
/ポロネーズ第5番 嬰ヘ短調 Op. 44
Nocturne in B flat minor Op. 9 No. 1
/ノクターン第1番 変ロ短調 Op. 9 No. 1
Scherzo in B flat minor Op. 31
/スケルツォ第2番 変ロ短調 Op. 31
さて今日は本命ピアニストが続きます。ショパントークでもお話しされていましたが、ボレロにノクターン1番に、こだわりがつまったプログラムです。やはり演奏とおして優しくて温かい。こんなに悲劇的なポロネーズもノクターンの延長線上にあるような。そしてノクターン1番を挟んでスケルツォ2番。コンクールだと3番、4番が多いイメージですし、そもそも今回は1次で選択できないので演奏機会が少ないなか、神秘的で美しいスケルツォでした。
10月12日(日)17:00(日本時間 翌0:00)
▼全体版:休憩中の「ショパン・トーク」にも注目!
Tomoharu Ushida (Japan, 1999) 3次ラウンド進出 ※1次ラウンド
piano: Steinway & Sons
Rondo à la Mazur in F major Op. 5
/マズルカ風ロンド ヘ長調 Op. 5
Sonata in B flat minor Op. 35
/ソナタ第2番 変ロ短調 Op. 35
Preludes Op. 28 Nos. 19–24
/前奏曲 Op. 28 No. 19–24
Polonaise in A flat major Op. 53
/ポロネーズ第6番 変イ長調 「英雄」 Op. 53
午後も注目ピアニストが続き、一人目は牛田さん。深い音楽性はもちろん、本質的ではないかもしれませんが、スケール感とか技巧とか、表面部分での変化をすごく感じ、「上品」や「深い音楽性」にとどまらないピアニストになってきた気がします。そしてソナタ2番を弾いたということは、3次では3番も聴けるわけですね!ぜひとも聴きたい。
Zitong Wang (China, 1999) 3次ラウンド進出 ※1次ラウンド
piano: Shigeru Kawai
Nocturne in F major Op. 15 No. 1
/ノクターン第4番 ヘ長調 Op. 15 No. 1
Ecossaise in D major [Op. 72 No. 1] (WN 13 nr 3)
/エコセーズ ニ長調 [Op. 72 No. 1] (WN 13 No. 3)
Ecossaise in G major [Op. 72 No. 2] (WN 13 nr 1)
/エコセーズ ト長調 [Op. 72 No. 2] (WN 13 No. 1)
Ecossaise in D flat major [Op. 72 No. 3] (WN 13 nr 2)
/エコセーズ 変ニ長調 [Op. 72 No. 3] (WN 13 No. 2)
Andante spianato and Grande Polonaise Brillante in E flat major Op. 22
/アンダンテ・スピアナートと華麗なる大ポロネーズ 変ホ長調 Op. 22
Ballade in A flat major Op. 47
/バラード第3番 変イ長調 Op. 47
Presto con leggerezza in A flat major (WN 44)
/プレスト・コン・レッジェレッツァ 変イ長調 (WN 44)
Preludes Op. 28 Nos. 19–24
/前奏曲 Op. 28 No. 19–24
Mazurka in F minor [Op. 68 No. 4] (WN 65)
/マズルカ ヘ短調 [Op. 68 No. 4] (WN 65)
1次ラウンドで強烈に印象に残っている注目ピアニストですが、これまた、、、すごいプログラム。コンクールではまず聴かない「ノクターン4番」、そして「プレスト・コン・レッジェレッツァ」は1918年に出版された短い前奏曲。そのまま24の前奏曲のクライマックスへとつながります。終曲24番ではこれまで見せなかった狂気が顔を出し、精根使い果たしたあとに空虚に響く遺作のマズルカ。もちろん残りのオーソドックスな曲も完成度が高い、特に、技巧的な大ポロネーズはこのレベルのコンクールでもトップクラスの出来でした。バラードや前奏曲24番含め、華やかな曲をプログラム途中で消化し、最後は現世から離れていくような終わり方で、演奏でもそれ以外でも鮮烈だったピアニスト。
Yifan Wu (China, 2008) 3次ラウンド進出 ※1次ラウンド
piano: Steinway & Sons
Preludes Op. 28 Nos. 13–18
/前奏曲 Op. 28 No. 13–18
Fantasy in F minor Op. 49
/幻想曲 ヘ短調 Op. 49
Andante spianato and Grande Polonaise Brillante in E flat major Op. 22
/アンダンテ・スピアナートと華麗なる大ポロネーズ 変ホ長調 Op. 22
Wangさんの後で引きづらそうだなと思いましたが、なかなか骨のある音色で華麗に決まりました。
Miki Yamagata (Japan, 2002) ※1次ラウンド
piano: Shigeru Kawai
Polonaise in A flat major Op. 53
/ポロネーズ第6番 変イ長調 「英雄」 Op. 53
24 Preludes Op. 28
/24の前奏曲 Op. 28
山﨑さんじゃなくて山縣さんが残ったのが意外でしたが、1次ラウンドよりも落ち着いて伸び伸び演奏されていたように思います。
William Yang (USA, 2001) 3次ラウンド進出 ※1次ラウンド
piano: Steinway & Sons
Barcarolle in F sharp major Op. 60
/舟歌 嬰ヘ長調 Op. 60
Nocturne in B major Op. 32 No. 1
/ノクターン第9番 ロ長調 Op. 32 No. 1
Nocturne in A flat major Op. 32 No. 2
/ノクターン第10番 変イ長調 Op. 32 No. 2
Andante spianato and Grande Polonaise Brillante in E flat major Op. 22
/アンダンテ・スピアナートと華麗なる大ポロネーズ 変ホ長調 Op. 22
Preludes Op. 28 Nos. 19–24
/前奏曲 Op. 28 No. 19–24
前半平穏なプログラム、舟歌にノクターン2曲は勇気がいりそうですが、柔らかい音色で素敵でした。そして後半では怒涛の技巧を披露してくれました。2次ラウンド最後のピアニストですが、技巧的にもかなり上位だったと思います。
4日目/2次ラウンドまとめ
4日間お疲れさまでした🙇
前回までは”差別化”を図れた「24の前奏曲」でしたが、このラウンド40名中10名が全曲演奏。そして時間的な制約からほとんどが「英雄ポロネーズ」をくっつけなければいけないことになりました。それでなくても前奏曲は全員が演奏しますし、一番人気は「19~24番」のクライマックスで、24番を演奏したピアニストが過半数。ピアニストは戦略的に難しい決断を迫られていたんですね。そんな中でもやはりレベルの高いコンクール、見ごたえのある2次ラウンドでした。
1日目:Yanyan Bao、Kai-Min Chang、Kevin Chen さんあたりは次も聴きたいですね。期待していたJacky Zhangさんは一次ほどは印象に残らず、応援していたJonas Aumillerさんもここまで奮ってない印象。
2日目:David Khrikuliさん、Tianyou Liさんはぜひファイナルまで残ってほしい。桑原 志織さんも相変わらずの安定感。Hyo Lee、Hyuk Lee兄弟は今回は弟さんの方が印象に残りましたが、お二人とも問題なく通過するレベル。Xiaoyu Huさんはどうかな、好きなところもありましたが。Zihan Jinさんも次聴きたかったですが、どうでしょう。
3日目:Eric Luの唯一無二の音楽はもちろん、リフレッシングな17歳Tianyao Lyu、気ままなVincent Ongさんは印象的、レトロで安心感のあるPiotr Pawlakの「演奏会用アレグロ」も絶品だったし、Ruben Micieliさんもほっとする演奏で充実した1日でした。次も聴きたい。
4日目:注目ピアニスト多数で大忙し!全員期待に違わぬ好演で見ごたえのある最終日でした。Hao Rao、Anthony Ratinov、進藤 実優、Gabriele Strata、牛田 智大、Zitong Wang、William-Yangさん、全員そろって3次ラウンドへ行ってほしい!!
結果~2次ラウンド~
発表は 51:00~辺り
3次ラウンド進出者(20名)[演奏日]
1. Piotr Alexewicz, Poland [10.9]
2. Kevin Chen, Canada [10.9]
3. Yang (Jack) Gao, China [10.9]
4. Eric Guo, Canada [10.10]
5. David Khrikuli, Georgia [10.10]
6. Shiori Kuwahara, Japan [10.10]
7. Hyo Lee, South Korea [10.10]
8. Hyuk Lee, South Korea [10.10]
9. Tianyou Li, China [10.10]
10. Xiaoxuan Li, China [10.11]
11. Eric Lu, USA [10.11]
12. Tianyao Lyu, China [10.11]
13. Vincent Ong, Malaysia [10.11]
14. Piotr Pawlak, Poland [10.11]
15. Yehuda Prokopowicz, Poland [10.12]
16. Miyu Shindo, Japan [10.12]
17. Tomoharu Ushida, Japan [10.12]
18. Zitong Wang, China [10.12]
19. Yifan Wu, China [10.12]
20. William Yang, USA [10.12]
以上の20名が進出しました。
そうですか。。。Yanyan Bao[10.9]、Hao Rao、Anthony Ratinov、Gabriele Strata[10.12]さんらはファイナルまで固いと思っていたし、3次のソロもすごく楽しみにしていたのですが。。。。Kai-Min Chang[10.9]、Ruben Micieli[10.11]さんらも通過してよさそうでしたが残念。。。
とはいえ、Kevin Chen、Eric Luさんは進出してますし、今大会でファンになったDavid Khrikuli、Tianyou Li、Tianyao Lyu、Vincent Ong、Piotr Pawlak、Zitong Wang、William-Yangなどまだまだ注目ピアニストも多数進出!Hyo Lee、Hyuk Lee兄弟は揃って3次ラウンド、すさまじい兄弟ですね。

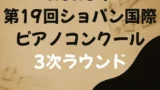


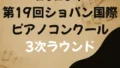
コメント