こんにちは。いりこです。
5年に一度開催される、世界一の知名度と権威を誇るショパン国際コンクールが2025年に開催されます。
2025年は大コンクールイヤー!
こちらの記事でまとめた15のコンクールのうち7つが開催されました。
ショパン国際と同じく「世界三大コンクール」と称されるエリザベート王妃国際に加え、バッハ国際、ロン=ティボー国際、クライバーン国際(特集なし)、ブゾーニ国際、クララ・ハスキル国際とみてきました。
そしていよいよ最高峰ショパン国際コンクール!5日間におよんだ1次ラウンドを経て、2次ラウンドには半分の40名が通過しました。
1日目から注目ピアニスト多数で大忙し!Jacky Zhang、Jonas Aumiller、Yanyan Bao、Kai-Min Chang、Kevin Chenさんが登場!
ショパン国際ピアノコンクール概要
公式HP(英語・ポーランド語):https://konkursy.nifc.pl/en/miedzynarodowy/konkurs
公式YouTube:https://www.youtube.com/@chopininstitute
知名度も権威も世界一と言っていい超名門ピアノコンクール。
大作曲家ショパンの名を冠し、祖国ポーランドが国を挙げて開催しているコンクールです。
演奏されるのはショパンの曲のみ!もちろんピアノ部門のみ!という独特なコンクールでもあります。5年に1度と開催間隔もかなり長く、歴史も長いです。
2020年はコロナで延期、満を持して開催された2021年大会は、反田と小林がW入賞して話題になりました。優勝者のブルース・リウ、ガジェヴやガルシアなど、タレント揃いで見ごたえのある大会でした。
- 概要
開催地:ワルシャワ(ポーランド)
開催期間:2025年10月2日(木)~ 10月23日(木)
開催間隔:5年に1度(第18回:2021年10月(2020年から延期)、次回:2025年)
歴史:第1回1927年

ちなみに過去の優勝者・入賞者は、クラシック界をけん引する錚々たるメンツ。名前を眺めるだけで鳥肌が立ちます!(笑)
- 主な優勝者・入賞者
優勝者:マウリツィオ・ポリーニ(1960)、マルタ・アルゲリッチ(1965)、ギャリック・オールソン(1970)、クリスティアン・ツィメルマン(1975)、ダン・タイ・ソン(1980)、スタニスラフ・ブーニン(1985)、ユンディ・リ(2000)、ラファウ・ブレハッチ(2005)、ユリアンナ・アヴデーエワ(2010)、チョ・ソンジン(2015)、ブルース・リウ(2021)
入賞者:ウラディミール・アシュケナージ(1955年第2位)、アルトゥール・モレイラ・リマ(1965年第2位)、内田 光子(1970年第2位)、横山 幸雄(1990年第3位)、ダニール・トリフォノフ(2010年第3位)、反田 恭平(2021年第2位)、マルティン・ガルシア・ガルシア(2021年第3位)、小林 愛実(2021年第4位)
▼過去大会の振り返り記事も併せてご覧ください!
2010年ショパンコンクールに耽る~アヴデーエワ/ゲニューシャス/トリフォノフ/デュモン~
2015年ショパンコンクールを振り返る~チョ・ソンジン/アムラン/ケイト・リウ/エリック・ルー/(トニー)・ヤン/シシュキン~
2021年ショパンコンクールを振り返る~ブルース・リウ/反田恭平/ガルシア・ガルシア/小林愛実/クシュリク/アルメリーニ/ラオ・ハオ~
スケジュール
予備予選(160名):2025年4月23日(水)~ 5月4日(日)
1次ラウンド(84名):2025年10月3日(金)~ 7日(火)
2次ラウンド(40名):2025年10月9日(木)~ 12日(日)
10月9日(木)10:00(日本時間17:00)、17:00(翌0:00)
10月10日(金)10:00(日本時間17:00)、17:00(翌0:00)
10月11日(土)10:00(日本時間17:00)、17:00(翌0:00)
10月12日(日)10:00(日本時間17:00)、17:00(翌0:00)
3次ラウンド(20名):2025年10月14日(火)~ 16日(木)
10月17日(金):ショパン没後176年目の命日
ファイナル(10名):2025年10月18日(土)~ 20日(月)
20日近くに及ぶ長丁場です。
プログラム
レパートリー:
参加者は、ビデオ審査で演奏した曲を本大会で演奏できる。
また、予備予選で演奏した曲も本大会で演奏できる(ただし練習曲を除く)。
本大会においては、同じ曲を異なるラウンドで演奏することはできない。
▼前回大会からの変更点を詳しく解説
【課題曲に大幅変更!】第19回(2025年)ショパン国際コンクール募集要項発表
2次ラウンド(40名)
• 6 Preludes from Op. 28, consisting of one of the following three groups:
/前奏曲 Op.28から、以下3つのグループのうちの1つからなる6曲:
7–12 or 13–18 or 19–24
• one of the following Polonaises:/以下のポロネーズから1つ
Andante Spianato and Grande Polonaise brillante in E flat major, Op. 22/アンダンテ・スピアナートと華麗なる大ポロネーズ 変ホ長調
Polonaise in F sharp minor, Op. 44/ポロネーズ第5番 嬰ヘ短調
Polonaise in A flat major, Op. 53/ポロネーズ第6番 変イ長調(英雄)
or both Polonaises from Op. 26/ポロネーズ第1・2番の両方
• any other solo piece or pieces by Fryderyk Chopin (the full Op. 28 is allowed).
/ショパン作曲の他のソロ作品(前奏曲 Op.28 全曲も可)
Performance time in the second round: 40–50 minutes.
/演奏時間は40~50分
The pieces may be performed in any order (except Op. 26).
/演奏順は問わない(ポロネーズ Op.26 を除く)
10月9日(木)10:00(日本時間17:00)
▼全体版:今大会も休憩中に「ショパン・トーク」が開催されるようです!他の大会にはないエンタメ性、魅力を発信しつづける素晴らしい姿勢ですね。
Jacky Zhang (UK, 2008) ※1次ラウンド
piano: Steinway & Sons
Polonaise in C sharp minor Op. 26 No. 1
/ポロネーズ第1番 嬰ハ短調 Op. 26 No. 1
Polonaise in E flat minor Op. 26 No. 2
/ポロネーズ第2番 変ホ短調 Op. 26 No. 2
24 Preludes Op. 28
/24の前奏曲 Op. 28
1次ラウンドでかなり上位に印象残っているピアニスト。ポロネーズ1,2番は久々聴きましたが、かっこいいですね。ドラマ性は薄いですけど彼は素朴な音色も上手です。前奏曲も随所に光るところはありましたが、やや散漫な印象も。あとは制限時間50分のところ、1時間近く演奏していたので影響がなければいいですが。
Piotr Alexewicz (Poland, 2000) 3次ラウンド進出 ※1次ラウンド
piano: Shigeru Kawai
24 Preludes Op. 28
/24の前奏曲 Op. 28
Polonaise in A flat major Op. 53
/ポロネーズ第6番 変イ長調「英雄」 Op. 53
前奏曲、音がこもってもったいない箇所などもありましたが、緩急がついていてよりインパクトがありました。特に弱音がとってーも美しい!
Jonas Aumiller (Germany, 2000) ※1次ラウンド
piano: Shigeru Kawai
Prelude in C sharp minor Op. 45
/前奏曲 嬰ハ短調 Op. 45
Polonaise in F sharp minor Op. 44
/ポロネーズ第5番 嬰ヘ短調 Op. 44
Preludes Op. 28 Nos. 13–18
/前奏曲 Op. 28 No. 13–18
Waltz in A flat major Op. 64 No. 3
/ワルツ第8番 変イ長調 Op. 64 No. 3
Fantasy in F minor Op. 49
/幻想曲 ヘ短調 Op. 49
前奏曲を全曲弾きたい気持ちもよくわかりますが、観客としてはこのようにいろんな曲や、ピアニスト独自のプログラム構成も楽しみたいですよね笑。さてアウミラーさん、ポロネーズ5番含めて随所に光るところはありましたが、んー、浜松で味わったほどの感動はまだ来ていない印象です。
Yanyan Bao (China, 2006) ※1次ラウンド
piano: Steinway & Sons
Preludes Op. 28 Nos. 13–18
/前奏曲 Op. 28 No. 13–18
Polonaise in C sharp minor Op. 26 No. 1
/ポロネーズ第1番 嬰ハ短調 Op. 26 No. 1
Polonaise in E flat minor Op. 26 No. 2
/ポロネーズ第2番 変ホ短調 Op. 26 No. 2
Waltz in A minor Op. 34 No. 2
/ワルツ第3番 イ短調 Op. 34 No. 2
Ballade in F minor Op. 52
/バラード第4番 ヘ短調 Op. 52
こりゃすごい。落ち着き払った音楽性を感じます。「雨だれ」のような美しい曲でも鬱々とした中間部のえぐみが際立っていますし、そのあとのポロネーズもしかり、暗いワルツしかり。極めつけはバラード4番。こんなん誰が弾いてもある程度素晴らしい曲に聞こえるようにできていますが、この方の演奏は、なんというか、憂鬱さがまとわりついてうっとうしい感じ。人生の中で辛い時間こそなかなか過ぎてくれないと思いますが、そのまさに最中にいる感じ。まだ19歳くらいでしょうか。ショパントークでの受け答えもかなり大人びていましたし、どんな人生を送ったらこんな演奏ができるのか。。。
Kai-Min Chang (Chinese Taipei, 2001) ※1次ラウンド
piano: Shigeru Kawai
Nocturne in C minor Op. 48 No. 1
/ノクターン第13番 ハ短調 Op. 48 No. 1
Preludes Op. 28 Nos. 19–24
/前奏曲 Op. 28 No. 19–24
Sonata in C minor Op. 4
/ソナタ 第1番 ハ短調 Op. 4
Polonaise in A flat major Op. 53
/ポロネーズ第6番 変イ長調 「英雄」 Op. 53
この方はショパンに限らず、いろんな曲が似合うんだろうなと思いますね。2024年リーズ国際でのベートーヴェンやブラームスもよかった記憶があります。今回は”習作”とされるソナタ1番。両端楽章はたしかにダサい冗長だと感じないこともないですが、印象的な2楽章メヌエットに、5拍子の3楽章ラルゲットは美しい。アシュケナージくらいし録音していないので、この曲が聴けると嬉しいですね。それから英雄ポロネーズもストレートにかっこいい!前回2021年は3次ラウンドに進めなかった(体調不良?)そうですが、今回は期待大!!
10月9日(木)17:00(日本時間 翌0:00)
▼全体版:休憩中の「ショパン・トーク」にも注目!
Kevin Chen (Canada, 2005) 3次ラウンド進出 ※1次ラウンド
piano: Shigeru Kawai
Preludes Op. 28 Nos. 7–12
/前奏曲 Op. 28 No. 7–12
Polonaise in A flat major Op. 53
/ポロネーズ第6番 変イ長調 「英雄」 Op. 53
Etudes Op. 10
/練習曲 Op. 10
これはまた一段と。。。前評判に違わず、優勝候補筆頭だと思いました。
まず前奏曲、この7~12番を選択する人なんかいるんだろうかと思っていたところ、プログラムのほんとに「前奏」の役割を持たせるにはこのチョイスかもしれません。それから英雄ポロネーズは大人しくすっきりした演奏。こんな大曲すら次のエチュードへの前奏??からのエチュードです。Op.10-1&2と、Op.25と合わせても上位に入る難曲から始まる鬼畜曲集ですが、これが鮮やか、、、でちょっと速い、、、でも美しい、旋律を浮かばせる余裕があります。そしてこれで1次ラウンドの爆速Op.25-6と合わせて難曲トップ3を全部弾いちゃいました笑。その後も技術的な不安が一切ない。音楽性や表現力はやっぱり技術的な基盤の上に乗ってくるものだと思いますので、ここで勝負できるピアニストは単純に強いと思います。しかもいわゆる派手で大衆受けする超絶技巧ではなく、音楽を表現するための土台という側面が強いところも、本物。個人的には隠れた難曲Op.10-7が鮮やかで、最後の「ドー」が絶妙で鳥肌が立ちました。
Xuehong Chen (China, 1999) ※1次ラウンド
piano: Steinway & Sons
Barcarolle in F sharp major Op. 60
/舟歌 嬰ヘ長調 Op. 60
Preludes Op. 28 Nos. 19–24
/前奏曲 Op. 28 No. 19–24
Prelude in C sharp minor Op. 45
/前奏曲 嬰ハ短調 Op. 45
Ballade in G minor Op. 23
/バラード第1番 ト短調 Op. 23
Polonaise in A flat major Op. 53
/ポロネーズ第6番 変イ長調 「英雄」 Op. 53
悪くなかったんでしょうが、前3人のインパクトが強すぎました。
Zixi Chen (China, 2002) ※1次ラウンド
piano: Shigeru Kawai
Fantasy in F minor Op. 49
/幻想曲 ヘ短調 Op. 49
Preludes Op. 28 Nos. 19–24
/前奏曲 Op. 28 No. 19–24
Rondo in C minor Op. 1
/ロンド ハ短調 Op. 1
Polonaise in A flat major Op. 53
/ポロネーズ第6番 変イ長調 「英雄」 Op. 53
相変わらず明るい音の伸びがすごく心地いいですし、細かいパッセージも緩急つけて表現できていました。ロンド1番 Op.1、こちらもソナタ4番同様演奏機会が少ないですが、アシュケナージくらいしか録音してないようなものなので、貴重な視聴機会ですね。
Yubo Deng (China, 2002) ※1次ラウンド
piano: Steinway & Sons
Polonaise in F sharp minor Op. 44
/ポロネーズ第5番 嬰ヘ短調 Op. 44
Ballade in F major Op. 38
/バラード第2番 ヘ長調 Op. 38
Preludes Op. 28 Nos. 19–24
/前奏曲 Op. 28 No. 19–24
Variations in B flat major on a theme from Mozart’s ‘Don Giovanni’ (‘Là ci darem la mano’) Op. 2
/モーツァルト「ドン・ジョヴァンニ」の「お手をどうぞ」の主題による変奏曲 変ロ長調 Op. 2
早速出てきましたラチダレム変奏曲。前回大会はブルース・リウ以外聴いた覚えがないので(だから鮮烈だった)、今回は3次も含めて増えてくるでしょう。演奏はブルースの偉大さが際立つ結果に。
Yang (Jack) Gao (China, 2003) 3次ラウンド進出 ※1次ラウンド
piano: Shigeru Kawai
24 Preludes Op. 28
/24の前奏曲 Op. 28
Polonaise in A flat major Op. 53
/ポロネーズ第6番 変イ長調 「英雄」 Op. 53
今日だけで3人が前奏曲全曲を演奏、この方とAlexewiczさんが同じくらいかな。英雄ポロネーズを残して立ち上がったのは間違えたのかも?笑、そのせいか英雄ポロはすこし抜けてた気もしますが、観客は異様な盛り上がり、んー、ショパン弾きかと言われると恣意的な感じも。
1日目まとめ
1日目お疲れさまでした🙇
Yanyan Bao、Kai-Min Chang、Kevin Chen さんあたりは次も聴きたいですね。期待していたJacky Zhangさんは一次ほどは印象に残らず、応援していたJonas Aumillerさんもここまで奮ってない印象です。

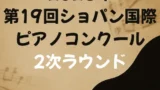


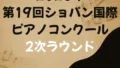
コメント